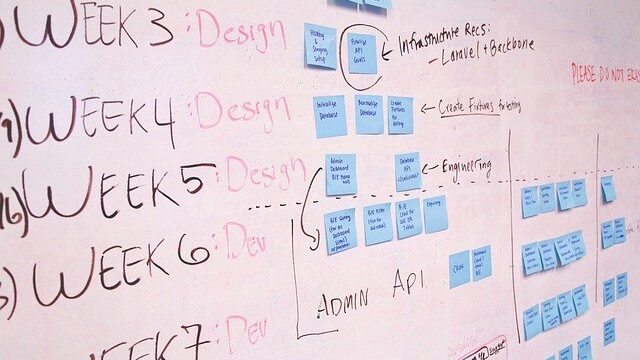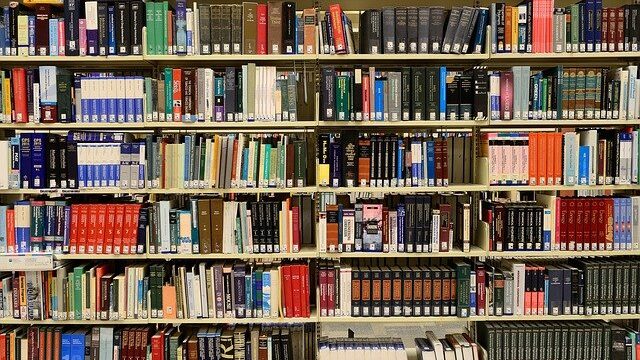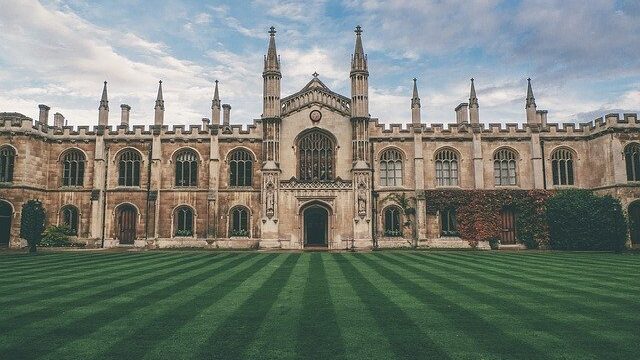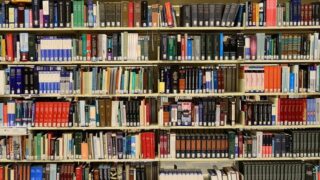地方上級市役所の受験の流れや出題科目や難易度などについて書いています。
また、地方上級(市役所大卒)に合格するためのおすすめの勉強方法などについても書いています。
■裁判所事務官一般職(大卒)の1次試験の流れ
■合格倍率
■合格ボーダー
■合格難易度
市役所の試験ではA日程、B日程、C日程と日程がわかれております。
それぞれの日程によって異なる部分や、市役所によっても違いがあります。
そのため、受験の流れや出題科目、難易度が全てに当てはまるわけではないので、ご了承ください。
私が受験した市役所の流れや、他の市役所の受験情報を元に書いています。
地方上級(市役所大卒)採用一次試験の流れ(主にA日程)
①受験案内などで試験日程や申込日が発表
②市役所採用試験説明会
③受験申込み
④1次試験受験
①受験案内などで試験日程や申込日が発表
受験案内や試験日程がインターネットの市役所の採用ページに発表されます。
受験申込み日などの情報を確認しておきましょう。
地方上級のA日程の場合、試験日が6月中旬になることが多いです。
年明けから受験先の採用ページを定期的にチェックしておくと良いです。
②市役所採用試験説明会
市役所によっては採用試験説明会がない場合もあるかもしれませんが、説明会がある場合には参加おすすめです。
説明会に参加することで、受験の流れなどや疑問点について教えて頂けます。
市役所によっては新卒の方などの話なども聞けると思います。
また、パンフレットなど面接対策にも使えると思いますので参加するべきだと思います。
私が受験した地方上級(市役所大卒)A日程試験の説明会は3月の中旬にありました。
6月にある国家一般職(大卒)などの説明会も同様に3月頃にありました。
そのため、6月頃の試験では3月ごろに説明会が行われることが多いと考えられます。
説明会ではほぼ全員スーツです。
面接用のスーツをまだ準備していない方は早めの準備がおすすめです。
③受験申込み
私が受験した地方上級(市役所大卒)A日程(6月中旬試験)の場合は5月の中旬にあり、1週間程度の申込期間でした。
申込み方法にはインターネット、郵送、持参の申し込み方法がありました。
最近ではインターネット申込みが増えていると思います。
私の場合、国家公務員試験などでもインターネット申込みをしていました。
そのため、インターネットでの申込みに抵抗がなく、インターネット申し込みの方が楽だと感じたためインターネットで受験申し込みしました。
友人の場合、地方上級A日程の市役所受験で、インターネット申込みが不安で、持参申し込みをしていました。
インターネット申込みは簡易で難しくなく、わりと簡単に終えました。
記入することは自分の簡単な経歴と、住所などの個人情報くらいでした。
市役所によっては志望動機も必要かもしれませんが、私の受験先では必要ありませんでした。
④1次試験受験
受験申込みの受験票や筆記用具などの必要な持ち物を忘れずに持って受験しましょう。
A日程の場合は、国家一般職の後の6月中旬のことが多いと思います。
1次試験に遅刻して受験できないのはとてももったいないです。
受験会場が遠い方は宿泊するのがおすすめです。
1次試験に遅刻して受験できないのは大変もったいないです。
受験会場が遠い方は宿泊するのがおすすめです。
前泊の体験談や試験前の宿泊についてこちらの記事に記載しております。
試験時間について
教養科目 2時間20分, 40問
専門科目 2時間, 40問
試験開始直後や終了直前でなければ、途中退出もできると思います。
また、市役所によっては異なる場合もあります。
私の受験した市役所では、教養試験は45問でした。
出題科目について
地方上級試験の日程や市役所によって出題科目は異なります。
A日程とB日程においては専門科目が必要になることが多く、C日程においては教養試験のみの場合が多い印象です。
市役所によって、科目の出題のされ方に差がある場合があります。
例えば、私の受験したA日程の教養試験では、全55問のうち、45問を回答でした。
また、専門試験においては、国家総合職と同じく、行政区分、法律区分、経済区分の選択ができました。
しかし、多くの市役所の場合は私が受験した市役所と異なり、問題やそれぞれの出題数が決まっており、問題を自分で選択回答できないと思います。
上記専門科目の科目の区分が選択できる場合、法律科目では経済学関係の科目が必要ではなく、経済区分では法律系科目が必要ありませんでした。
行政区分の場合は法律科目および経済科目の両方が出題される区分になっておりました。
一般的な地方上級市役所大卒の試験はこの行政区分にあたる出題科目になると思います。
教養試験の科目
文章理解、数的処理・判断推理、資料解釈、自然科学、人文科学、社会科学、時事
他の試験と同様に文章理解、数的処理・判断推理が出題数が多いです。
また、時事は社会科学の中にも出題されていますので、時事も実際には出題数が多いと思います。
専門試験の科目
憲法、民法Ⅰ、民法Ⅱ、行政法、ミクロ経済学、マクロ経済学、財政学、経済事情、政治学、行政学、刑法、労働法、国際関係、社会政策
他の試験種と同様に憲法、民法Ⅰ、民法Ⅱ、行政法、ミクロ経済学、マクロ経済学、財政学が出題数が多いです。
また、財政学や経済事情では時事の内容を含む問題が出題されることも多いです。
地方上級試験合格に必要な点数
地方上級試験のA日程、B日程、C日程で合格に必要な点数は変わってくるかなと思います。
地方上級試験A日程における合格に必要な点数は大体6割程度だと思います。
難しいところで、6割5分程度になるのかなと感じました。
C日程において教養科目のみ試験の場合は6割~8割が必要になることもあると思います。
教養試験のみの場合は、教養試験のみを重点的に勉強している人がいることや、倍率も高いため、合格点数が高くなるのだと思います。
とにかく基本が大切だと思いました。
試験まで勉強期間がある方や、模試で結果が出ていない方は今一度勉強方法を見つめ直すことをおすすめします。
私が使ってみて、おすすめの参考書や過去問をこちらにまとめています。
地方上級(市役所大卒)1次試験の難易度
★★☆☆☆~★★★★☆
市役所によって、倍率や難易度が異なってくると思いますので2~4としました。
地方上級A日程の多くの場合は★★★☆☆かなと感じています。
私の受験先は私の受験年度では合格者数が多く、倍率も低かったため合格しやすかったです。
ですが、少し以前(3年前以降)の受験年度を見ると倍率もかなり高く難しそうでした。
受験先の受験年度によっても倍率が変わり、合格難易度は変わると思います。
私の受験先では説明会のときに退職者が多く、採用も多くなるということを言っておりチャンスだということを知りました。
国家一般職、裁判所事務官、国家専門職などの試験に比べて、問題の難易度が低く感じました。
特に数的処理・判断推理や文章理解を解いたときに、問題の難易度の差について実感しました。
過去問や参考書の基本的な問題が多い印象でした。
地方上級(市役所大卒)では基礎が大切だと感じました。
そのため、同じく6割程度が合格に必要な国家公務員系よりも1次試験の難易度は低いかなと感じました。
しかし、市役所の倍率によっては合格に必要な点数も高くなるため、国家公務員よりも難しい場合もあると思います。
私の主観ですが、地方上級の日程別の難易度は、
C日程>B日程>A日程かなと思います。
A日程試験の場合、採用人数が多いこともありC日程よりも倍率が低いことが多いと思います。
また、C日程の場合は教養試験のみのことも多く、その場合、合格に必要な点数も高くなります。
そのほかC日程は教養試験のみを勉強してきた人がいること、他の試験が不合格であり、その後みんなさらに勉強して受験していることなどがあるのかなと思います。
最短合格のススメ
公務員試験大卒の一次試験を効率よく最短合格の勉強方法はこちらにまとめております。
また、おすすめ過去問題集や参考書はこちらにまとめております。