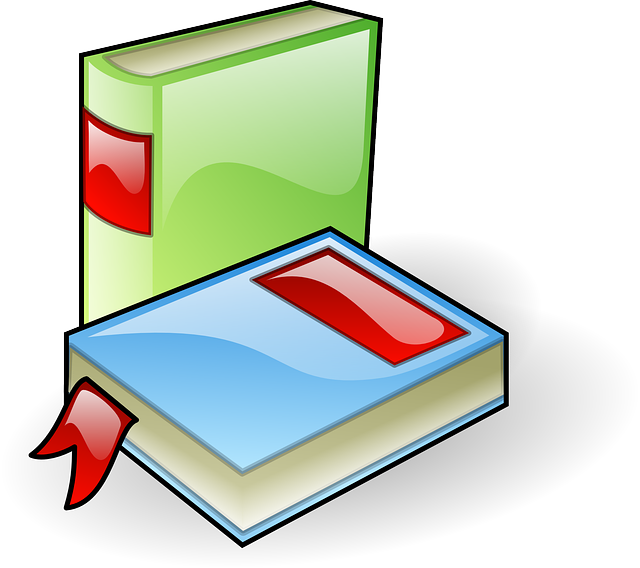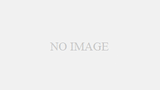公務員試験(大卒)の合格において、参考書と過去問問題集は効率に直結する部分であり、大変重要です!
その理由は、参考書と過去問問題集は、細かい内容を含めると、勉強する量が膨大すぎてしまいます。
合格までのレベルを短い時間3ヶ月~1年の勉強期間で身に付ける人場合、
あまり試験に出題されない部分も含めて勉強すると、
重要なところへの勉強時間が少なくなってしまい効率性を損ないます。
なので、ぶ厚い本ほど良いというのは失敗しがちです!
参考書は網羅生が高すぎず、かつ、出題される重要部分にフォーカスしており合格に必要なボリュームがあるものが良いです。
また、解説が詳しく、分かりやすいものがおすすめです。
公務員(大卒程度)試験の教養科目と専門科目のそれぞれのおすすめの参考書と過去問問題集を以下まとめております。
教養科目のおすすめ参考書と過去問問題集
数的処理・判断推理
公務員試験における数的推理・判断推理は法律科目や社会科学などの過去問などで暗記する科目とは少し異なり、基礎から身に付ける必要がある科目だと思います。
ただ公式や問題の答えを覚えればいいというものではなく、その公式を用いると何がわかるのか、問題の解答がどういう過程で求められるのかをきちんと理解する必要があります。
なぜなら、実際の公務員試験では過去問問題集と同じような問題も出題されますが、少し変えたり、捻ったような出題もあるからです。
数的処理と判断推理共に出題数は他の科目よりも多く、最重要科目になると思いますので、自分のレベルにあった参考書でじっくり勉強するのがおすすめです。
[玉手箱]
玉手箱は基礎的な問題から学ぶことができます!
玉手箱は数学が苦手な方にとってとてもおすすめです。
予備校に通っていない独学の方で、計算が得意でない場合はこの本から勉強すると基礎を身に付けることができると思います。
玉手箱は少し簡単な問題を使って、解法をわかりやすくじっくり学ぶことができます。
解法パターンを学ぶのにとても良い参考書で、畑中敦子のカンガルー本よりも初学者の方にとっては先にこちらをマスターするのをおすすめします。
[カンガルー本]
数的推理と判断推理はカンガルー本がとてもおすすめされています。カンガルー本とは本の表紙がカンガルーなのでカンガルー本と言われています。
その他、ワニの表紙のワニ本などがあります。
カンガルー本は試験の問題に近い良問を解くことができ、とても良い参考書でした。
解説や見やすさなども使いやすく良かったです。
また、Play、Try、Challengeにレベル別で分かれており、また、試験別の出題傾向や頻出度も記載されています。私の場合、まずはPlayとTryである程度の問題ができるようにPlayとTryを6周程度して身につけました。
Challengeまで手を出すと、1周にかかる時間が増えてしまい、あまり勉強時間に余裕もなかったため、基本を着実にこなせたのはとても良かったです。
カンガルー本を解いてみて、難しいようであれば、まずは玉手箱などできっちり基礎を身につけてから、使用することをおすすめします。
カンガルー本はとても良問であり、解説もしっかりしているので、何周も解き理解しながら学習しましょう。解き方の流れがすぐに頭に浮かぶくらいにはなっておくべきです。
ChallengeはPlayとTryを十分できるようになってから着手するのがおすすめです。市役所試験や国家一般職の場合はChallengeまでできなくても十分だと思います。
数的処理と判断推理の詳しい勉強方法については以下にまとめています!
資料解釈
資料解釈とは、文章を読んで理解してその内容と正しいものを選ぶというような文章理解とは異なり、グラフや数表、統計などから数字を読み取り、割合などを計算し選択しと同じものを選ぶという問題になります。
例えば、年代別に映画公開本数が書かれており、1990年の映画公開本数は2000年の映画公開本数の6割以下である、というような他の年代と比較して計算するような選択肢が5つあります。
計算するだけなので、時間をかければ多くの人が解くことができますが、公務員試験では試験時間が限られています。
特に、教養試験では、時間がかかり問題数の多い文章理解や数的推理・判断推理があります。
資料解釈ではいかに短時間で数値を見つけ、正確に計算できるかが重要です。
そのため、はやく見つけること、割合などの計算に慣れることやテクニックが必要になります。
[カンガルー本]
資料解釈はあまり出題数も多くないということ、計算は割と得意な方であるため、勉強をあと回しにしていました。
後回しにして試験2ヶ月前くらいになって少しは勉強しておこうと思いました。
予備校のテキストは資料解釈の問題が少なかったこともあり、また、数的処理と判断推理の畑中敦子さんのカンガルー本がとても良いということを知ったので、資料解釈においてもカンガルー本から着手しました。
資料解釈を勉強する時間はあまりなかったため、基礎問題と基本問題のみ何度か解きました。
2-3周程度しか周回できなかったため、残念ながら身に付いたかどうか怪しい感じでした。
畑中敦子さんの資料解釈The Best+(カンガルー本)は、数的処理と判断推理と同様にとても良問が多く、解説やテクニックが分かりやすいためおすすめです。
インプット編とアウトプット編に分かれています。
インプット編では必要な知識やテクニックを効率よく学ぶことができます。
インプット編では問題数こそ少ないですが、基礎的な問題が用意され、短い時間で頻出パターンを網羅することができます。
また、基礎でじっくりテクニックに慣れることができます。
パターンごとの頻出度、重要度、コスパも表示されているので、時間がない人はコスパいいのところだけを選択して学習することもできます。
アウトプット編では、超基本、基本、標準、やや難しい、難レベルに分かれており、レベルに合わせて勉強部分を選ぶことができるので時間がない方は標準まで勉強するというように決めることで、効率よく勉強できます。
資料解釈という科目は出題数が多くはないため、重要度の高い科目ではありません。
他の重要科目が十分にできてから取り組むと良いと思います。
試験まで余裕がない方は捨てても良いと思います。教養科目では、数的処理や判断推理、文章理解などで、時間に余裕がないため、割り切って他の科目に時間を使うのは返って良い場合もあると思います。
文章理解
中学高校の試験やセンター試験の国語と英語の試験に近い問題です。
日本語または英語の本文を読んでその内容や趣旨に最も近いものを選ぶ問題になります。古文も出題されますが、近年古文の問題数が減り、英語の問題数が増えてきております。
地方上級や国家一般職の試験種によって出題数は変わりますが、古文は多くて1,2問になります。
1,2問のために古文の単語など勉強して時間をかけるのはもったいないので、古文は捨てても大丈夫だと思います。
ただ、英語は問題数も増えてきており、教養の中でも割合は多い方なので、苦手な方も多いと思いますが、捨てるべきではないと思います。
スーパー過去問問題集
文章理解を勉強するときに、始め使った参考書でした。
私は中学高校のときから国語が苦手でした。
選択肢と本文の内容がほとんど一緒に感じてしまい引っかかりや二択で間違えてしまうことが多かったです。
スー過去で毎日勉強していれば、理解力が上がり得点できるようになっていくだろうと思っていました。
しかし、勉強しても一向に文章理解の成績は上がる気がしませんでした。
先に問題を見てから解くのがコツというのを頻繁に見ましたが、全然できませんでした。
悩みに悩んで文章理解直観ルールブックで解き方を知り、得点がみるみる伸びました。
スー過去は文章理解の解き方を学ぶよりは、問題数も多いため、文章理解の解き方を使って演習するのにとても良いと思いました。
私も文章理解直観ルールブックの後に、スー過去でテクニックやコツをつかむのに使用しました。国語だけでなく、英語も同様です。
文章理解直観ルール
公務員試験 文章理解 すぐ解ける〈直感ルール〉ブック[改訂版] amzn.to
1,890円 (2025年04月19日 12:03時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
文章理解直観ルールブックはとてもおすすめの参考書です。
私は文章理解が原因で、教養科目の過去問を解いても6割を超えることができませんでした。
スー過去などの勉強で正答率が上がる気配が感じられず悩んでいたときに見つけたのがこの参考書でした。
その当時、ネットなどで文章理解のおすすめ本を探していましたが、あまりこの本がおすすめされているのを見かけませんでした。
(見逃していただけかもしれませんが)
なので、この参考書のテクニックで点数が上がるのか不安でしたが、この本のテクニックを実践してみると、驚くように解けるようになりました。
文章理解が得意科目になっており、8割は正解できるようになりました。
この参考書は国語だけでなく、英語の解き方も載っているのでとても良いです。
英語が苦手な人もこの解き方を学ぶと得意にはならないかもしれませんが、また、英語そのものができるようになるかはわかりませんが、公務員試験の英語の正答率が上がるのではないかと思います。
文章理解が苦手な方はぜひご一読おすすめです。
英単語Core1900
速読速聴・英単語 Core1900 ver.5 amzn.to
3,140円 (2025年04月19日 12:05時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
英単語と時事的な内容の文章があり、公務員試験の英語の勉強におすすめされていました。
私は文章理解直観ルールブックで勉強する以前は、この本で英単語を覚えつつ、文章を精読していました。
しかし、上記国語と同様に点数が上がる気配が全くありませんでした。
結果的に直観ルールブックで解けるようになりましたが、英単語の勉強には使って良かったなと思いました。
英単語はスー過去では勉強しにくいので、英単語用に購入するのにおすすめです。
基礎単語から時事に良く使われる単語を勉強できるため、英語が苦手な方にとてもおすすめです。
自然科学・人文科学
自然科学は中学高校の理科、人文科学は中学高校の社会や歴史に近い範囲になります。
自然科学は化学、物理、生物、地学、数学人文科学は日本史、世界史、の問題がまとまった科目になります。
自然科学・人文科学は教養試験の科目の中であまり多い出題数ではありません。
以下のダイレクトナビまたは過去問解きまくりのどちらかの勉強で十分だと感じました。
ダイレクトナビ
上・中級公務員試験 過去問ダイレクトナビ 物理・化学 amzn.to
1,430円 (2025年04月20日 11:16時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
上・中級公務員試験 過去問ダイレクトナビ 生物・地学 amzn.to
1,430円 (2025年04月20日 11:17時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
上・中級公務員試験 過去問ダイレクトナビ 日本史 amzn.to
1,430円 (2025年04月20日 11:17時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
上・中級公務員試験 過去問ダイレクトナビ 世界史 amzn.to
1,430円 (2025年04月20日 11:18時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
上・中級公務員試験 過去問ダイレクトナビ 地理 amzn.to
1,430円 (2025年04月20日 11:18時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
ダイレクトナビの良かったところは、どこが間違っているのかがとてもわかりやすいです。また、解説ものっているので便利です!
選択肢のどこが間違っていて、どこを訂正したら正解の文になるかがわかるというのは、他の参考書にはない特徴です!
また、問題数もとても少なく、短い時間で1周を終えることができます。
私はどちらの参考書も使って勉強しました。始めにダイレクトナビを使って、生物・地学の勉強をしました。
その次に物理・化学の勉強もしました。
しかし、途中で物理や化学の問題で計算問題がのっていないことに気づきました。
また、問題量が少なく、どうしても不安に思ってしまいました。
それと、赤シートで隠しての勉強は私には向いていない気がしました。
そのため、「過去問解きまくり」に途中から変更しました。「過去問解きまくり」は頻出部分を活用して範囲を絞って勉強しました。
「過去問解きまくり」がシンプルで適度な量で私には合っていたな~と思います!
「過去問解きまくり」
2025-2026年合格目標 公務員試験 本気で合格!過去問解きまくり! 【5】人文科学I(最新 ! 24年度問題収録)(教養試験対策) (公務員試験過去問解きまくりシリーズ) amzn.to
1,980円 (2025年04月19日 12:08時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
2025-2026年合格目標 公務員試験 本気で合格!過去問解きまくり! 【6】人文科学Ⅱ(最新 ! 24年度問題収録)(教養試験対策) (公務員試験過去問解きまくりシリーズ) amzn.to
1,980円 (2025年04月19日 12:08時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
過去問解きまくりは、ダイレクトナビやスー過去よりも各テーマの問題数も多く、安心して取り組むことができました。
しかし、その分ボリュームもいっぱいで、時期的にテーマを絞って学習するしかありませんでした。
1問選択肢5つが左ページにあり、右ページに解答解説ついているため、スー過去よりも学習しやすいなと思いました。
また、文字数も多すぎず、色も私は好きだったので嫌になりませんでした。
テーマを絞るときには、頻出部分や過去の傾向も見れるので、それを見て決めていました。
社会科学
社会科学は、政治、法学、経済、社会の問題が出題されます。
時事的な問題も含むため、時事を勉強していると解ける問題も多いです。
また、法学では憲法や民法の範囲と被る部分があります。
経済では専門科目の経済学と被る部分があります。
このように社会科学は専門科目や時事に含まれる問題が多くあります。
社会科学は専門科目を勉強した後に勉強した方が勉強の負担が減ります。
社会科学の参考書や過去問を見ると、その分厚さと範囲に圧倒されます。
いきなり、勉強しても頭に入ってきにくい科目だと感じました。
また、時事や専門科目をしっかり勉強していれば、頻出だけを対策していれば十分の科目かもしれません。
おすすめしている「過去問解きまくり」はかなり分厚いですが、範囲を絞って余裕が出てからの勉強がおすすめです。
社会科学のスー過去は問題数が少なすぎるわけでもないため、スー過去での勉強も良いかもしれません。
インプットが少し多いのと、問題数が多いため、私は「過去問解きまくり」で勉強しました。
「過去問解きまくり」
2025-2026年合格目標 公務員試験 本気で合格!過去問解きまくり! 【4】社会科学(最新 ! 24年度問題収録)(教養試験対策) amzn.to
2,090円 (2025年04月20日 11:22時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
社会科学のクイックマスターはかなり分厚いです。
初学者がこの本を見ると、公務員試験で合格できる気がしないかもしれませんが、全てを完璧に網羅する必要はありません。
私の場合も、じっくり社会科学の勉強に時間を設けることができなかったこともあり、頻出テーマ部分を選んで、その他の部分は捨て範囲として全く勉強しませんでした。
ですが、時事や専門科目を勉強していたおかげで、本番で社会科学の正答率が悪いということはありませんでした。
クイックマスターの問題は良問で、問題数も適量で良かったです。なにより、試験別に範囲別に過去の出題数が分かるので、それを見て勉強範囲を選択できて良かったです。
時事
公務員試験で出題数が多い数的処理・判断推理や専門科目だと憲法、民法、経済学などは重視され、公務員試験の受験生にも最重要科目として認知されています。
しかし、それと同じくらい時事は重要な科目です。隠れ主要科目などと言われることもあります。
出題数などを見ると、時事は出題として少ないなと思うこともあるかもしれません。
しかし、教養試験では社会科学などにおいて、専門科目では財政学などで時事の内容が出題されることが多いです。
その他の科目でも、時事で勉強した内容が絡んでいることがあります。
そのため、時事は重要な科目です。
その時事を勉強する上でおすすめの参考書は、速攻の時事と速攻の時事トレーニングです。
速攻の時事
公務員試験 速攻の時事 令和7年度試験完全対応 (教養試験対策) amzn.to
1,320円 (2025年04月20日 11:24時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
時事の勉強は速攻の時事がおすすめです。
速攻の時事は他の参考書よりも薄いですが、内容はとても濃いです。思いのほか1周読むのに時間がかかりました。
初めてのことや細かな数値も覚える必要があるので、厚さの割りに情報量は多かったです。
この薄さで本当に大丈夫なのか不安でしたが、実際の試験ではかなり効果がありました。
細かな数値なども意外と重要ななので、もっと時間をかけて何周も読んで勉強すれば良かったなと思いました。
毎年その年の受験用に発売され、また、時事ということもあり、他の科目の参考書と異なり、受験年度ごとに内容が前年度と異なる部分も多いです。
そのため、受験年度の速攻の時事を購入するのがおすすめです。試験前の2月,3月頃に発売されます。
それ以前から受験勉強しており、時間に少しゆとりがある場合は、受験年度の速攻の時事と被る部分もあるため、発売が直前なため、前年度のものを購入して勉強しても良いと思います。
速攻の時事トレーニング
公務員試験 速攻の時事 実戦トレーニング編 令和7年度試験完全対応 (教養試験対策) amzn.to
1,210円 (2025年04月20日 11:25時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
速攻の時事だけでは、読んだ内容を覚えているか、これで問題が解けるか不安だったので、一緒に発売されていた速攻の時事トレーニングを購入しました。
速攻の時事トレーニングはクイックマスターやスー過去のような問題と解説が記載されており、演習ができるのでおすすめです。
予想問題がついているのはとても良かったです。
速攻の時事のようにインプット部分もありましたが、やはり速攻の時事の方が情報量は多いです。
私は速攻の時事と速攻の時事トレーニングを併用して交互に勉強して、細かな数字部分など少しずつ覚えました。
時事はとても重要な科目だと思いますので、じっくり併用して勉強するのがおすすめです。
専門科目のおすすめ参考書と過去問問題集
専門科目で重要な科目は、法律系は憲法、民法、行政法となります。経済系はミクロ経済学、マクロ経済学が特に重要です。
法律系と経済系は並行して勉強するのが良いと思います。
法律系は憲法→民法→行政法の順で、経済系はミクロ経済学→マクロ経済学→財政学の順がおすすめです。
憲法
専門科目のうち法律系の科目であり、法律系で出題数も多く重要な科目です。
憲法は国の基本となる法律です。憲法については何となくイメージできる方も多いと思います。
人権であったり、信教の自由、表現の自由などの勉強をしていきます。
また、三権分立の国会・内閣・裁判所などについても勉強します。
憲法の科目では、このような人権などでの事件における判例などが出題されることが多いです。
始めはとても難しく感じるかもしれません。
また、過去問題集ではなく、予備校のテキストやインプット系の文章で説明が膨大にあり、圧倒されてしまうかもしれませんが、過去問題集ができるようになれば大丈夫です。
全てを暗記する必要はなく、重要なポイントを抑えることが大事です。
そう言った面から過去問問題集のスー過去から始めるのがとてもおすすめです。
スー過去
憲法のスーパー過去問ゼミはとても良かったです。
憲法は全くの初学者でしたが、スー過去の問題を何度も繰り返すことで、模試試験や実際の試験で正解していくことができました。
憲法のスー過去の良いところはやはり、過去問の厳選による良問で効率的に勉強できます。
また、網羅的で試験で見たことがないという問題はほとんどありませんでした。もう一つは解説の詳しさです。
これにより、理論を理解できていなくてもこの解説を覚えることで正解することができました。
憲法は予備校でほとんど授業も出席せず、スー過去のみの勉強で十分でした。憲法をスー過去で何周も勉強するのがおすすめです。
民法Ⅰ,Ⅱ
専門科目のうち法律系の科目であり、法律系で出題数も多く重要な科目です。
民法は法律の中でも私たちの身の回りで一番身近な法律だと思います。
例えば、不動産などの物権変動であったり、未成年の代理や、相続についてなどがあります。
ただし、憲法よりも難しく、また、暗記だけでは対応できないところもあり理解も大切だと思います。
私の場合も、専門科目では民法が一番苦手でした。
しかし、出題数が多く、またⅠ、Ⅱと分かれており、Ⅰ、Ⅱそれぞれに多くの出題があるため、避けては通れない重要な科目です。
スー過去だけでもある程度同じ問題であれば正解できるようになると思いますが、スー過去だけでは理解が難しい点があり、基礎を理解するためにもまるごと生中継で勉強してからスー過去で勉強するのがおすすめです。
まるごと生中継
郷原豊茂の民法 (1) 新・まるごと講義生中継 第2版 (公務員試験 まるごと講義生中継シリーズ) amzn.to
1,540円 (2025年04月20日 11:32時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
郷原豊茂の民法 (2) 新・まるごと講義生中継 第2版 (公務員試験 まるごと講義生中継シリーズ) amzn.to
1,707円 (2025年04月20日 11:32時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
スー過去では理解できなかった論理的な点や、スー過去で出てくる法律用語などについて簡単に説明してあり、とても理解しやすいです。
絵やイラストでの説明であり工夫されています。
授業の黒板で説明しているのが本になったような感じです。私の通っていた予備校の民法の授業よりも大変わかりやすかったです。
まるごと生中継で勉強するのが遅くなったことや勉強時間が少なかったこともあり、1,2周しか勉強できなかったため、理解したところを結局スー過去で解くときにあれ、どうだったっけと忘れてしまいました。
早いうちからまるごと生中継で基礎を固めてからスー過去で問題演習、試験前にもう一度復習のような勉強ができれば良かったなと思います。
スー過去
民法のスー過去も憲法と同様とても良い過去問問題集です。
スー過去は民法が必要な場合、ほとんどの受験生がこれで演習を行うくらい必須の本だと思います。
私はまるごと生中継を勉強する前に、スー過去から基礎的な語句など知らないまま勉強しました。
語句の意味などわかりませんでしたが、こういう問題でこういうパターンのときはこうなるというのが暗記に近いですが、わかるようになりました。
スー過去のみの勉強でも地方上級(市役所)や国家一般職では6割程度は取れるかもしれません。
ただ、安定的に6割以上取れるようになるため、民法が苦手にならないためにもまるごと生中継の勉強と両方で勉強するのがおすすめです。
行政法
行政とは、司法と立法以外で国を治める作用のことで、国家機関や地方公共団体がこれに当てはまります。
行政法は、そのような行政を規律するための法律です。
憲法、民法Ⅰ,Ⅱと同様に出題数は多い科目であり、法律系科目の重要な科目です。
行政法は民法より馴染みはありませんが、民法よりはほんの少し易しいかもしれません。
民法と同様に、まるごと生中継→スーパー過去問問題集の勉強がおすすめです。
憲法や民法よりも行政法は改正される頻度が多いため、スー過去や参考書は中古の過去年度ではなく、最新版の購入が推奨です。お気を付けください。
まるごと生中継
新谷一郎の行政法 新・まるごと講義生中継 (公務員試験 まるごと講義生中継シリーズ) amzn.to
1,760円 (2025年04月20日 11:33時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
民法と同様に、難しい語句や用語であり初学者には難しい科目です。
まるごと生中継では基礎的な語句や用語の説明、なぜそのような法律なのかがイラスト付きでわかりやすいため、苦手意識が減るかもしれません。
民法や憲法と同様に、受験生の大半がこの本で対策をしており、この本の反復で試験対策ができます。
とても良問であり、網羅性も高いため、この本での演習は推奨です。
ミクロ経済学, マクロ経済学
ミクロ経済学では、消費者理論や生産者理論やパレート最適などについて勉強していきます。
マクロ経済学では、財市場、貨幣市場、債権市場、労働市場などについて、関数や図によって分析していきます。
一次関数や二次関数、簡単な微分などがあり、文系出身の場合は苦手にする方も多いです。
難しそうに見えるかもしれませんが、試験を解く分にはある程度パターン化された計算になるため、苦手意識を持たずにしっかり演習をすることがおすすめです。
らくらくのたまご→らくらくミクロ経済学およびらくらくマクロ経済学→スーパー過去問問題集の順での勉強がおすすめです。
時間に余裕がない場合はらくらくミクロ経済学とらくらくマクロ経済学からでも良いと思います。
また、時間がなく数学がある程度わかる場合はいきなりスー過去でも良いと思います。
らくらくシリーズ
試験対応 新・らくらくミクロ経済学入門 (KS専門書) amzn.to
2,420円 (2025年04月20日 11:35時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
試験対応 新・らくらくマクロ経済学入門 (KS専門書) amzn.to
2,420円 (2025年04月20日 11:35時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
らくらくシリーズは、数式、理論的な部分や解き方の理解に初学者にわかりやすく優しいので、最初に勉強するのがおすすめです。
らくらくはスー過去よりも簡単な問題であるため、基礎から学ぶことができます。
また、理論的な部分の理解がしやすくなっています。
私の場合、計算がある程度できたこと、模試でスー過去のみで高得点が取れていたため、らくらくシリーズを購入して勉強しませんでした。
しかし、実際の試験では国家一般職や国家総合職の試験で少し問題が難しくなると解けませんでした。
スー過去では繰り返すことである程度問題は解けるようになりますが、基礎的な理論部分が欠如してしまい応用に対応できませんでした。
その点、らくらくからしっかり基礎を身につけて勉強するのが良いと思いま
す。
スー過去
法律系科目と同様に、ミクロ経済学、マクロ経済学においてもスーパー過去問問題集が演習では推奨です。
私はスー過去のみでしたが、多くの試験で6割-9割程度取ることができました。
経済学の問題はある程度パターン化されているため、詳しく問題解説がされているため、スー過去の解き方を学習すると、ある程度に対応できました。
ただし、解き方はわかるようになりますが、基礎的な部分、インプット用の説明はかなり少ないです。
そのため、少し応用問題があると対応できないときがありました。
国家総合職や国家一般職の少し難しめの問題以外、ミスはあっても全くわからないという問題はありませんでしたが、らくらくシリーズでしっかり理解しながらスー過去に取り組むのがおすすめです。
財政学、経営学
財政学では、予算やGDPなどといった国の財政を扱った問題が出題されます。
経営学においては、組織における作業効率をあげるための実験などを学びます。
社会で勤務経験がある方はOJTやISOなど馴染みのあるものも出てきます。
どちらの科目も暗記科目になります。
ただし、覚える範囲は多く、時間はかかります。
財政学は国家一般職の選択科目に含まれ、地方上級でも出題される自治体が多いため、勉強しなければならない方も多いと思います。
ただし、地方上級(市役所)において、財政学は憲法、民法などの法律系科目や経済学の科目に比べて出題数が少ない傾向にあり、また、財政学は時事での勉強と重複するところも多いため、財政学の勉強に費やす時間は法律系科目と経済科目の主要科目に比べると少なくて良いと思います。
経営学は財務専門官、国税専門官、国家一般職の選択科目で出題されます。
地方上級(市役所)の試験では出題されないところが多いと思います。
また、財務専門官、国税専門官においては出題数が多いほうではありません。
国家一般職も選択のため、他の科目を選択すれば良いため、経営学の科目は勉強しない方も多いと思います。
私の場合は財務専門官が第一志望だった時期もあり、また、地方上級よりも国家一般職などの方を志望していたため、経営学や財政学の勉強をしました。
速攻の時事と速攻の時事トレーニング
こちらは上記時事のところと同じものになります。
財政学で時事の予算などの部分が頻出であるため、時事で勉強しておけば取れる部分もあります。
そのため、時事の範囲はしっかり勉強しておくことがおすすめです。
経営学では時事の内容はほとんど出題されません。
私の場合、財政学は速攻の時事シリーズとスー過去、経営学はスー過去のみを勉強しました。
スー過去で6割程度は安定して取れるようになりました。
経営学は範囲が広いこと、時間の比重がすくなかったことなどから、試験では記憶があいまいで自信を持って回答できませんでしたが、スー過去で十分だと思います。
経営学はそれほど重要な科目ではないため、時間をかけすぎない方が良いと思います。
財政学の場合は、数値がその受験年度によって変わるため、最新版で勉強する必要があるので、注意が必要です。
財政学のスー過去での勉強時、前年度との数値の違いなど大切なので意識するのおすすめです。
スー過去で解けるようになるか、不安でしたが、実際の試験ではスー過去に似た問題も多く、案外得点できました。
その他おすすめ参考書
公務員試験マル秘裏ワザ大全
新版 公務員試験マル秘裏ワザ大全【国家総合職・一般職/地方上級・中級用】 amzn.to
1,470円 (2025年04月20日 11:40時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する
書店などで公務員試験マル秘裏ワザ大全を手にとって、気になった方も多いのではないでしょうか?
この本は袋とじになっており、購入しなければ見ることができません。
三日で合格!と書かれているけど、本当だろうか?と思う方もいると思います。
この本のテクニックをお伝えすることはできませんが、
正直、この本だけで公務員試験に合格できるほど公務員試験は甘くはありません。
しかし、この本は他の参考書とは違い、得点を上げれるテクニックの面で優れています。
ただし、確実に正解できるというわけではありません。選択肢を絞るのに役に立ちます。
公務員試験で過去問などを解いていると、これは間違いの選択肢だいうのがあります。
例えば、~はどんなときでも~である。や、~は絶対~である。といった絶対というような表現は公務員試験では選択肢として誤りのことがほとんどです。
そのため、選択肢を絞ることができます。
この本のみで合格は難しいですが、運よりは正答率を上げられる可能性が高く、じっくりこの本を取り組む必要はないと思いますが、一公務員試験において役に立つので時間があれば一読するをがおすすめです。
おすすめ本まとめ
■教養科目
・文章理解[重要]
英単語Core1900、文章理解直観ルールブック→スーパー過去問問題集
・数的処理と判断推理[重要]
玉手箱→カンガルー本
・自然科学・人文科学
過去問解きまくりorダイレクトナビ
・社会科学
過去問解きまくり、速攻の時事
・資料解釈
カンガルー本
時事[重要]
速攻の時事、速攻の時事トレーニング
■専門科目
法律系
・憲法[重要]
スー過去
・民法Ⅰ,Ⅱ[重要]
まるごと生中継→スーパー過去問問題
・行政法[重要]
まるごと生中継→スーパー過去問問題
経済系
・ミクロ経済学、マクロ経済学[重要]
らくらくシリーズ→スーパー過去問問題集
・財政学
スー過去、(速攻の時事)
■その他
・経営学
スー過去
・その他科目
公務員マル秘